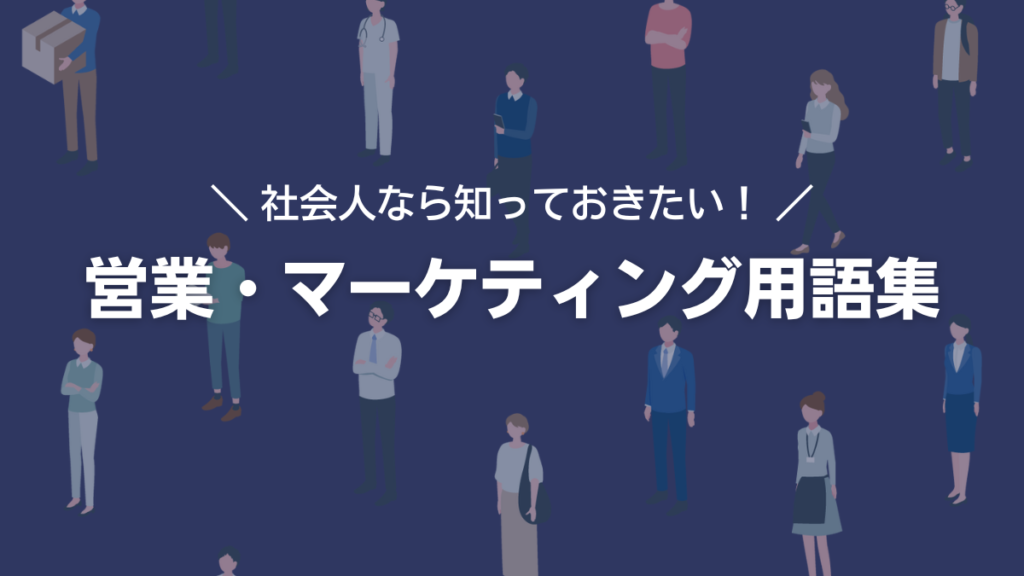
初心者から上級者まで、営業・マーケティングの現場で使われる専門用語をわかりやすく解説。
すぐ使える知識をサクッとインプットできる、営業・マーケティング用語集です。
わからない用語がでてきたら、その場で解決!
辞書やFAQの代わりに使えるので新人教育にも活用できます。
◆インサイドセールス
CDP
顧客一人ひとりの属性データや行動履歴を集め蓄積するデータプラットフォームで、デジタルマーケティングに不可欠です。氏名や電話番号などの個人情報に加え、行動履歴なども含めたファーストパーティーデータを収集します。ユーザー情報を収集・分析するDMPとは、データの内容や収集元が異なりますが、CDPはより個人情報に近いデータを蓄積します。
CMS
コールセンターの運営を管理するシステムです。コール数や通話時間などをデータベース化し、可視化します。スーパーバイザーがリアルタイムで状況を把握し、長期的なデータ分析を通じて生産性向上や適切なオペレーター配置を可能にします。これにより、顧客ロイヤルティ向上にも貢献します。
CRM
顧客との良好な関係を築き、顧客生涯価値(LTV)向上を目指す取り組み、またはそのためのツールを指します。顧客情報や行動履歴を一元管理し、個々に適切なサービスを提供することで、顧客数の増加に伴う管理の課題を解決します。連絡先や購入履歴、問い合わせ内容、商談状況などを共有し、LTVの高い顧客分析から新規獲得にも繋げられ、インサイドセールスには不可欠です。
CRP
顧客への価値提供に関わる全プロセスを指します。営業担当が顧客との信頼関係を築くための活動を可視化したCRPマップは、顧客が期待する価値を継続的に提供するための分析に用いられます。顧客体験を軸とするカスタマージャーニーマップとは異なり、CRPマップは価値提供と信頼関係構築が目的です。
CS
顧客満足度を指し、購入した商品やサービスについて顧客がどの程度満足しているかを数値化したものです。CS向上をめざすには、カスタマーサクセスの考え方が重要です。カスタマーサクセスとは顧客の成功体験づくりを積極的にサポートする活動で、どんなニーズがあるのかを把握したうえで取り組む必要があります。
csvファイル
Comma Separated Valuesの略で、拡張子は「.csv」です。カンマで値を区切ったファイル形式を指します。データ容量が軽く互換性が高いのが特徴ですが、文字や記号のみで構成されますが、住所や日付が意図しない形式になったり、電話番号の先頭の0が消えたりすることがあるため、営業リストとして扱う際は注意が必要です。
CTI
コンピュータと電話の機能を連携させ、管理する技術の総称です。インサイドセールスやコールセンターなど電話業務において、顧客データと電話内容を自動連携することで、作業効率化と成果向上を目指します。顧客情報表示や通話録音など、担当者が過去データや受注確度を参照しながら通話できる機能を提供します。
DB
データを一定の形式で整理し、蓄積や検索を容易にしたものです。主にコンピューター上のデータを指します。既存顧客の購買履歴をデータベースに蓄積して分析することで、自社の商品やサービスに反応しそうな顧客を抽出して、クロスセルやアップセルなどの戦略に役立てることができます。このような手法を「データベースマーケティング」といいます。
DMP
Data Management Platformの略で、インターネット上に蓄積されたユーザーの行動履歴や属性データ、広告配信データなどを一元的に管理し、マーケティング活動に活用するプラットフォームです。
EFO
入力フォーム最適化を意味し、ユーザーがWebサイトなどの入力フォームで離脱しないよう、使いやすい環境へ改善することです。BtoB企業ではリード獲得の成果を左右し、コンバージョン率に直結します。近年はサジェスト機能などアシストツールも手軽に利用できるため、EFOツールの導入も検討するとよいでしょう。
MA
マーケティング活動の自動化・効率化を指し、そのためのツールも含まれます。見込み顧客の創出から育成、営業がアプローチすべきリードの選定までの一連のプロセスを自動化・効率化します。メールマーケティング、LPやフォーム作成、CRMやSFAとの連携機能を備えたツールもありますので、活用していきましょう。
MQL
Marketing Qualified Leadの略で、リードナーチャリングにより購買確度が高まった見込み顧客を指します。営業部門へ引き継がれ商談に進みます。よく似た言葉のSQL、TQL、SALとの違いも覚えておきましょう。
PBX
構内交換機と訳され、大きな組織で複数の電話機を設置する際に、内線通話や外線着信制御を可能にするシステムです。従来のPBX専用機に加え、近年はインターネット通信を利用したIP-PBXや、通信事業者が提供するクラウドPBXがあります。インサイドセールスやコールセンターでは、CTIシステムと連携させて電話業務に活用されています。
SDR
インサイドセールスの一種で、マーケティングからのリードを商談化し営業へ引き継ぐインバウンド型です。BDRは新規顧客開拓のアウトバウンド型営業。ADRはマーケティングからの見込み顧客リストを評価し、営業への引き継ぎを判断する役割を担います。
SFA
営業支援を目的とした業務効率化ツールです。営業プロセスを自動化し、顧客情報や活動状況をデータベース化、蓄積・分析します。商談履歴や進度、担当者ごとの活動がリアルタイムで可視化され、営業活動の効率化と標準化に貢献します。営業支援と案件管理に特化しており、CRMやMAとの連携が一般的です。
SGL
セールスジェネレイテッドリードの略で、営業部門が創出したリードを指します。よく似た言葉に「MQL」と「SQL」があります。
STP戦略
営業活動において、案件発生から受注・納品までの所要時間を指します。営業フェーズごとに必要な時間を可視化することで、関係者間の認識合わせに役立ちます。営業がコントロール可能なフェーズでは、リードタイムの短縮が求められます。また、顧客の意思決定を支援するための戦略的なサポートも重要です。
アイスブレイク
初対面の相手との緊張を和らげ、コミュニケーションを円滑にするための手法です。ビジネスでは、初対面の取引先との関係構築や、チーム内の相互理解を深め、活発なコミュニケーションを促すために活用されます。
アクティブリスニング
積極的に相手の話に耳を傾け、理解しようとする「積極的傾聴」を意味する心理学用語です。コールセンターなどのビジネスシーンでは、顧客との効果的なコミュニケーションや関係構築に不可欠なスキルとされます。ただ話を聞くのではなく、顧客の会話から問題点や要望を引き出し、自己解決へと導くことが本質です。顔が見えないテレマーケティングでは、特に重要な姿勢です。
インサイドセールス
営業形態の一つで、見込み顧客のリスト化からアポ取り、訪問、クロージングまでの非対面業務を指します。「内勤型営業」とも呼ばれ、SDR(反響型)とBDR(新規開拓型)の二つの手法があります。
インバウンド
顧客へのアプローチ手法で、「内向きの」インバウンドと「外向きの」アウトバウンドを指します。現代では、購入前の情報収集がインターネット中心のため、アウトバウンドよりもインバウンドへの注目が高まっています。
エンゲージメント
ビジネスにおいて、顧客が企業に対して感じる愛着や結びつきの強さを示す言葉です。エンゲージメントが強いほど良好な顧客関係が築け、契約継続や製品活用につながります。顧客との良好な関係構築を目指すマーケティング手法を「エンゲージメントマーケティング」と呼びます。
オープンクエスチョン
相手から多くの情報を引き出すため、自由に答えてもらう質問を指します。一方、クローズドクエスチョンは回答範囲を限定し、相手の考えを明確にします。ニーズヒアリングにはオープンクエスチョン、商談やクロージングにはクローズドクエスチョンの組み合わせが効果的です。
オンラインセールス
インターネットを利用した営業活動全般を指します。インサイドセールスはリード創出から商談化までを担いますが、オンラインセールスは従来の対面式営業だったフィールドセールスの役割をオンラインで代替するものです。その具体的な範囲は企業によって異なります。
クロージング
営業活動における契約の成立を意味します。ヒアリングと提案を経て、成約へ導く最終工程です。高単価な商材ほど難易度が高く、商談中に購入意欲や懸念点を確認する「テストクロージング」などのテクニックが有効です。
コールドコール
面識のない相手に電話をかける、いわゆる飛び込み型の電話営業手法で、「コールドリスト」を用います。相手のニーズなどが不明なまま架電するため、受付ブロックされる可能性が高いです。コストは抑えられますが、成果には多くのコール数が必要なため、ターゲティングで興味を持つ可能性の高い企業に絞るのが重要です。
コールドリード
将来的に商品やサービスを購入する可能性はあるものの、まだ興味が薄く検討段階に至っていない見込み顧客を指し、「潜在顧客」とも呼ばれます。メルマガやセミナーなどで継続的にアプローチすることで、購買意欲を高めていくことが重要です。
コール数
オペレーターが電話をかけた件数を指します。インサイドセールスでは、コール数、通電数、アポイント数がKPIとして設定されます。コール数を増やしてもアポイント数が増えるわけではないため、リストの精度向上やトークスクリプトの改善、SFAの導入などが常に必要です。
データクレンジング
CRMやSFAなどのデータベースから不要なデータを除き、品質を高めることです。古くなった情報の更新や、重複・誤記・表記ゆれの修正を行い、データを扱いやすくします。名寄せの前に実施し、データ統合時の重複や誤りを防ぎます。
データドリブン
定量的なビッグデータを分析し、企業の意思決定や課題解決に繋げる業務プロセスを指します。インサイドセールスでは営業活動の効率化や成約率向上に役立ちます。ただし、適切なツール導入とデータの正確な蓄積・運用が不可欠です。
デマンドジェネレーション
案件創出を意味し、マーケティング活動で得られたホットリストをフィールドセールス部門へ引き渡すまでの一連の活動を指します。リードジェネレーション、リードナーチャリング、リードクオリフィケーションの3ステップで構成されます。BtoB企業ではリードナーチャリングが特に重要です。
テレアポ
電話でアポイントを取る手法を指します。即座に反応が得られる利点がある一方、架電数に限りがあります。メルアポはメールでアポイントを取り、手間は少ないものの開封率向上の工夫が必要です。
テレマ
電話を使って、見込み顧客や既存顧客に商品やサービスの購入を促進する手法を指します。販売促進や満足度向上を目的としたダイレクトマーケティングで、主に電話をかけるアウトバウンドが多いのが特徴です。
トラッキング
ユーザーの行動を追跡し、分析することを指します。Cookie情報を参照し、Webサイト閲覧履歴や滞在時間を把握することで、ユーザーの興味度合いを測れます。広告の効果測定や改善にも役立ち、デジタルマーケティングにおいて費用対効果を明らかにする手法です。
トリガー
顧客が何らかの行動を起こすきっかけとなるマーケティング施策を指します。インターネット広告やメルマガ、SNSなどが例として挙げられます。MAツールのシナリオ機能では、顧客のオンライン行動をトリガーとして設定し、自動でメールを配信できます。
パイプライン
パイプラインは、営業活動における案件獲得から受注までのプロセスを指します。成約までの一連の流れを可視化し、分析・改善するパイプライン管理が、SFAの導入により注目されています。
ハウスリスト
マーケティング活動などで獲得された見込み顧客リストを指し、企業名、担当者名、連絡先などの情報を含みます。リードナーチャリングに活用され、その質の確保と量がリードジェネレーションに求められます。常に最新情報に更新し、CRMやSFAで活動履歴などを共有することが重要です。
ペルソナ
提供する商品やサービスを最も利用しそうな架空のユーザー像を設定するマーケティング概念です。年齢、性別、職業、趣味など詳細な設定を加え、非常にリアリティの高い人物像を作り上げます。顧客像を統一し、商品開発やマーケティング活動の検討に役立てるメリットがあります。
ホワイトリスト
見込み顧客のデータベースであり、特定の選定基準に合致する企業のみをリストアップし、集中的なアプローチで売上を最大化することを目的とします。これはABM(Account Based Marketing)と呼ばれる営業・マーケティング手法の一つです。営業活動で失注した際は、その理由を分析し、リストの選定基準を更新することも重要となります。
リード
自社の商品やサービスを購入する可能性のある見込み顧客を指します。リードは獲得経路や興味関心度合いによって細かく分類されます。マーケティング活動で獲得したMQL、電話営業で獲得したTQL、営業部門に引き渡されたSAL、商談化されたSQLなどです。また、興味度合いによりコールド、ウォーム、ホットリードに分けられ、それぞれに最適なアプローチが行われます。
リードクオリフィケーション
リード(見込み顧客)の中から、購買や商談化の可能性が高い顧客を絞り込むプロセスを指します。リードジェネレーション、リードナーチャリングに続くステップです。絞り込みには、企業規模などの基本スコアに行動スコアを合算する「スコアリング」が用いられます。これにより購買意欲を判断し、効率的な営業活動を実現します。
リードジェネレーション
見込み顧客(リード)を獲得するための活動を指します。WebサイトやSNSなどのオンライン、広告や展示会などのオフラインでリードを獲得します。獲得したリードを育成し商談や成約に繋げる「リードナーチャリング」と対をなす概念です。BtoBマーケティングやインサイドセールスの要となります。
リードスコアリング
リード(見込み顧客)やそのステージを数値化する手法を指します。定性的な評価ではなく、属性や行動などの事実に基づき客観的に指標化します。MAツールを導入して自動でスコアリングを行うこともあり、これにより適切なタイミングでのフォローや優先順位付けが可能になります。
リードソース
リード(見込み顧客)の獲得方法や獲得元を明らかにしたものです。獲得経路を分析することで、商談化率の高いソースや低いソースを可視化できます。チャネルごとに分類し、リードソース別にアプローチ方法を変えるのも営業手法の一つです。
リードナーチャリング
マーケティング施策で獲得したリードを育成し、成約に繋げる手法です。リードの課題を理解し、ニーズを顕在化させた上で、適切な解決策を提供します。メルマガ、セミナー、Webコンテンツ、テレマーケティングなど、中長期的なコミュニケーションで興味関心度合いが上がったタイミングで商談に繋げます。
リードマネジメント
リードの獲得から育成、商談化までを一貫してフォロー・管理することを指します。新規顧客獲得だけでなく、既存顧客の離脱防止も含まれます。顧客情報や行動履歴を分析し、適切なアプローチで機会損失を回避します。膨大な顧客情報を管理するため、MA、SFA、CRMなどのツール導入が不可欠です。
リードリサイクル
一度失注したリード(見込み顧客)を再度商談化するために、リードナーチャリング(見込み顧客育成)を行うことを指します。リードジェネレーションからクオリフィケーションの過程で減少したリードや、商談後に失注したリードに再度アプローチします。SFAやMAツールを活用し、失注リストを管理することが重要です。
営業リスト
新規顧客開拓やテレアポなどの営業活動に必要な企業情報のリストを指し、「アタックリスト」や「コールリスト」とも呼ばれます。企業名、連絡先、担当者名などが記載されます。インサイドセールスでは営業担当者名やアプローチ履歴なども記録し、SFAなどのツールで管理することで効率的な運用が可能です。
架電
電話をかけることを意味し、法律用語が一般化したものです。電話がかかってくることは受電といい、顧客へかける電話はアウトバウンド、顧客からの電話はインバウンドと呼びます。インサイドセールスでは架電数をKPIとし、通話時間と合わせて行動量を測ります。コールセンターツールによる自動記録やAIによる会話解析も進んでいます。
見込み顧客
自社の商品やサービスを購入する可能性のある顧客を指し、「リード」とも呼ばれます。メルマガ登録や資料請求などが該当します。潜在顧客は自社サービスを知らない、またはニーズに気づいていない顧客です。見込み顧客と顕在顧客に明確な違いはなく、どちらも自社サービスへの関心が高い顧客です。
現アナ
未使用電話番号にダイヤルした際に流れる「現在使われておりません」というアナウンスを指す、コールセンター用語です。コールセンターシステムによっては、自動で未使用電話番号を検出し、オペレーターの時間を短縮し、テレマーケティングの精度を高める機能を持つものもあります。
受付ブロック
テレアポ時に受付を突破できず、担当者に繋いでもらえない状況を指します。不在や類似サービスの利用、営業電話の取り次ぎ拒否などが理由です。担当者名が不明なリストへのテレアポでは発生しやすく、トークスクリプトの改善で受付ブロック率を下げることが重要です。
潜在顧客
自社の商品やサービスを知らない、またはニーズが顕在化していない顧客を指します。新規顧客は、自社の商品やサービスを初めて購入した顧客です。顧客は「潜在顧客」「見込み顧客」「新規顧客」「既存顧客」に分類され、それぞれリードジェネレーション、リードナーチャリング、カスタマーサクセスといった施策でアプローチされます。
待ち呼
コールセンターにかかってきた電話に対応できず、顧客が待機している状態を指します。顧客満足度低下を防ぐため、オペレーター増員やシステム導入による対応時間短縮が必要です。待ち呼の件数や応答率は、コールセンターの状況把握と最適化の指標となります。
追客
潜在顧客を追う営業行為を指し、不動産業界などで重視されてきました。現在では、マーケティング部門が集めた潜在顧客に対し、インサイドセールス部門が様々な手法で営業をかける主業務を指す言葉にもなっています。追客活動の目的は、潜在顧客と長期的な接点を持ち、信頼関係を築きながら顧客を育成することです。
名寄せ
複数のデータベースから同一人物や同一企業のデータを統合し、一つにまとめることを指します。データの不備や重複を防ぎ、顧客リストの正確性を担保します。SFAやCRM導入時、また営業リストを扱う際にも定期的な実施が必要です。名寄せの前に、表記ゆれなどを修正するデータクレンジングを行うと精度が向上します。
◆BtoB営業・マーケティング
3C分析
企業のマーケティング戦略を立てる際に用いられる市場分析フレームワークです。顧客、競合、自社の3つの視点から分析し、成功要因(KSF: Key Success Factor)を見つけることが主な目的です。これにより、事業の方向性を明確にできます。近年では、流通などを加えた発展形も存在します。
ABM
BtoB企業向けのマーケティング戦略です。個人のリードではなく、特定の企業(アカウント)をターゲットとし、そこにリソースを集中させます。自社にとって価値の高い顧客を選び、その企業に合わせた最適な戦略でアプローチすることで、利益の最大化を目指します。
AIDMA
AIDMA、AISAS、AMTUL、ASICAは、顧客の購買プロセスを示す代表的なフレームワークです。これらを理解することで、マーケティング戦略においてどの段階のコミュニケーションを改善すべきか把握できます。
BANT
営業において案件の有望度を測るためのフレームワークです。予算、決裁権、必要性、導入時期の4つの要素から顧客を分析し、受注確度を判断します。元々は営業の手法でしたが、近年ではマーケティング分野でも活用されています。
BtoBマーケティング
企業が他の企業へ製品やサービスを提供するマーケティング活動を指します。消費者向けのBtoCとは異なり、BtoBでは予算規模が大きく検討期間も長くなるため、戦略も大きく変わります。
BtoB営業
企業が他の企業へ商品やサービスを販売する営業を指します。消費者へ販売するBtoC営業と異なり、主に素材、ITサービス、人材などがBtoB営業の代表例です。
LP
LP(ランディングページ)は、検索結果や広告からの流入後、最初に表示されるWebページです。商品の購入やお問い合せといったコンバージョン獲得が目的で、1ページ完結型で縦長なのが特徴。流入経路やキーワードごとに内容を最適化でき、効果的なLPには営業トークを元にした決まった型もあります。
PEST分析
PEST分析は、自社を取り巻く外部環境が与える影響を分析するフレームワークです。Politics(政治)、Economy(経済)、Society(社会)、Technology(技術)の4つのマクロ要因を分析し、変化する環境下での自社の位置付けや戦略の方向性を検討するために用いられます。
PPM分析
経営資源の最適な配分を検討するフレームワークです。市場成長率と市場占有率を軸に、事業や製品、サービスを「花形」「金のなる木」「問題児」「負け犬」の4つに分類します。これにより、各事業の将来性や競合との売上格差を数値で把握し、投資配分を判断できます。
PRM
パートナーリレーションシップマネジメントの略で、企業とビジネスパートナーが長期的に良好な関係を構築するためのマーケティング手法です。製品情報やノウハウ共有を通じてビジネスプロセスを合理化し、利益拡大を目指します。顧客関係管理のCRMとは異なります。
RFM分析
顧客をグループ分けするマーケティングフレームワークです。直近の購入日、購入頻度、購入金額の3つの指標で顧客をスコア化し、グループに合わせた効果的なマーケティング施策を可能にします。これにより、無駄を省き、マーケティング活動全体の効率を高めます。
SEO
インターネット上の検索エンジンを活用し、自社サイトへの訪問者を増やすマーケティングの総称です。
STP戦略
マーケティング戦略のフレームワークです。市場をニーズや特性で細分化(セグメンテーション)し、注力する顧客層を決定(ターゲティング)。その後、ターゲット市場で製品やサービスの独自の地位を確立(ポジショニング)し、競合優位性を目指します。
SWOT分析
事業におけるプラスとマイナス要因を、外部と内部の環境から分析する手法です。強み(Strength)と弱み(Weakness)という内部要因、機会(Opportunities)と脅威(Threats)という外部要因の4つを分析。目的は、内外の重要要因を特定し、内部は強化・改善、外部は活用・回避するなど、それぞれに応じた対策を立てることです。
オウンドメディア
自社が所有・運用するメディア全般を指します。ホームページやブログ、メルマガなどが該当し、時間や労力はかかりますが、永続的に利用でき、高い集客力が期待できます。企業紹介や採用活動、リードナーチャリングにも活用できます。他社がコントロールするレビューサイトやSNSなどはアーンドメディアと呼び、これとは異なります。
カスタマーサクセス
顧客の成功体験を支援するビジネス手法です。企業の商品やサービスを通して顧客が成果を出せるようサポートし、顧客満足度を高め、解約率を下げ、企業の利益向上を目指します。顧客の課題を早期に解決し、サービス改善に繋げることで、顧客ロイヤルティとLTV向上に貢献します。
カスタマージャーニー
顧客が商品やサービスを認知し、購入・利用に至るまでの行動、思考、感情を時系列で可視化するものです。ネット社会で複雑化した顧客行動において、接点を把握し、課題解決とブランド価値向上に役立ちます。
コンテンツマーケティング
顧客にとって価値ある情報を発信し、育成から購買、ファン化へと繋げるマーケティング手法です。SNSでの商品紹介やカタログ送付などが例で、積極的に売り込むのではなく、情報提供で顧客との関係維持を目指します。近年、オンライン販売の増加に貢献しています。
ダイレクト・レスポンス・マーケティング
の営業と異なり、反応のあった消費者層に絞ってアプローチするため効率的。これにより成約に近い見込み顧客のリストを作成でき、成功率が格段に向上します。
チャネル
顧客を集める媒体や経路のことです。LPやリスティング広告、キャンペーンなどが該当し、多様なチャネルを持つことで多くの消費者を集められます。テレビやWeb広告などのコミュニケーションチャネル、流通業者や卸売業者といった流通チャネル、小売業者やEコマースの販売チャネルに分けられ、良い商品でもチャネルが悪いと売れないほど重要です。
バリュープロポジション
顧客にとって有益な「提供価値」を示すマーケティング用語です。顧客のニーズが高く、競合他社にはない独自の価値を提供することで集客や売上向上を目指します。顧客がその商品を選ぶ理由となり、顧客視点での製品開発やマーケティングにも活かせます。
ファネル
「漏斗(ろうと)」という意味で、集客から成約に至るまで、顧客が絞り込まれていく様子を漏斗状に図式化したものです。
ホワイトペーパー
「白書」を意味する言葉ですが、近年は企業が課題解決策として自社ソリューションを紹介するダウンロード資料を指します。リード獲得施策として活用され、ダウンロードと引き換えに企業情報などを得ます。Webサイトからのリード獲得だけでなく、有益な情報発信によりリードナーチャリングも可能です。
マーケティング
商品が自然に売れる仕組み作りです。顧客のニーズを理解し、適切な商品を開発から宣伝、販売までの一連の活動を通して最適な顧客層に届けます。「買いたい」と思わせることに本質があり、市場調査、広告宣伝、効果検証のプロセスを辿ります。特にインサイドセールスでは、Webマーケティングによるリード創出も含まれます。
メールマーケティング
メール配信を通じて顧客とコミュニケーションをとるマーケティング手法です。新商品案内からお礼メールまで幅広く、メルマガもその一種。紙媒体より低コストで始められ、潜在・見込み顧客に効率的にアプローチできます。MAツールで効果検証も容易で、効率的なマーケティング活動が可能です。
ラポール
フランス語で「橋を架ける」を意味し、心理学では親密な繋がりを指します。ビジネスでは、顧客との信頼関係構築を指し、売上に繋がるとされます。単純接触効果が重要で、接触回数が多いほど好感度が増すという研究結果もあります。顧客以外に、上司や部下との関係構築にも活用できます。
リスティング広告
検索エンジンの検索結果に連動して表示される広告です。Google広告やYahoo!広告が代表例で、クリックごとに費用が発生するクリック課金型が多いです。ユーザーが検索したキーワードに合わせ表示されるため、購買意欲の高い層に直接アプローチでき、売上につながりやすいメリットがあります。一方で、競合が多いと広告費用が高くなる可能性があります。
リテンション
既存顧客を維持するマーケティング手法をリテンション、新規顧客獲得をアクイジションと言います。会社の売上にはリテンションが重要です。新規顧客獲得には既存顧客の5倍のコストがかかるとされ、これを「1:5の法則」と呼びます。リテンションは、特典や手厚いサポートで解約を防ぎ、売上維持・向上に繋がります。
リレーション
「関係」や「繋がり」を意味し、ビジネスでは取引先や顧客との信頼関係を指します。マーケティングでは、顧客との良好な関係を築く手法、リレーションシップマーケティングを指します。顧客のニーズや悩みを解決し、長期的な関係維持と利益向上を目指す営業スタイル、リレーションシップ営業も存在します。
ロイヤルカスタマー
企業の商品やサービス、企業自体に愛着を持つ顧客を指します。企業の売上の大部分を占めることもあり、新規顧客獲得よりもコストを抑えつつ収益確保に貢献します。リピート購入に加え、他者への推薦も期待でき、接触頻度を上げるなど特別な顧客体験を提供し育成することが重要です。
休眠顧客
過去に取引があったものの、現在はない顧客を指します。市場縮小で新規獲得が難しい今、休眠顧客へのアプローチは重要です。特にBtoBビジネスでは、取引額が大きく次に必要になるまでの期間が長いため、定期的なアプローチで休眠顧客を掘り起こす施策が重視されます。
◆営業戦略・営業ノウハウ
BSC
バランスドスコアカード(BSC)は、ビジョンと戦略を明確にし、財務以外の経営状況や経営品質も含めて多角的に評価する業績評価手法です。「財務の視点」「顧客の視点」「内部プロセスの視点」「学習と成長の視点」の4つの視点から戦略目標を捉え、多面的な指標で評価します。これにより、企業の収益拡大や社内変革、新しいビジネスモデルの創出に繋がります。
CAC
Customer Acquisition Costの略で、新規顧客を獲得するためにかかったマーケティングとセールスに関する費用全体のことを指し、顧客獲得単価を意味します。宣伝広告費だけでなく、営業人件費なども含めて全体の費用を把握することで、損益分岐点を確認しながらマーケティング投資が可能になります。
Cookie
Webサイト閲覧時にユーザーの訪問履歴や入力情報などをブラウザに一時保存するファイルです。ログイン情報の再入力省略や、ユーザーに合わせた広告配信を可能にします。近年、プライバシー保護のため規制が強化されており、特に複数のサイトを横断して追跡するサードパーティーCookieの利用にはユーザーの同意が必要です。
CP
コストパフォーマンス(コスパ、CP)は、費用の対効果を比較したものです。消費者は満足度、企業は数値を基準とします。そのため、安価であることが必ずしも良いコスパを意味しません。コスパを上げるには、開発から販売までの流れを数値化し、料金と人的コストの違いを理解することが重要です。
CPA
Cost per Acquisitionの略で、コンバージョン1件あたりの広告費用です。CPOは「Cost per Order」の略で、本商品の受注1件あたりの広告費用を指します。CPRは「Cost per Response」の略で、サンプル請求や問い合わせなど見込み顧客の申し込み1件にかかる広告費用です。
CPC
Web広告が1回クリックされるごとに発生する費用「クリック単価」のことです。これは「広告費÷クリック数」で計算され、広告の費用対効果を示す重要な指標となります。クリックされるまで費用はかからず、予算上限も設定できるため、運用次第で費用対効果の高いマーケティングが可能です。ただし、CPCが低すぎると誤クリックが多い、あるいは需要がないなどの問題が考えられます。
CSR
Corporate Social Responsibilityの略で、企業が果たすべき社会的責任です。消費者、取引先、従業員、投資家、地域社会、環境など、様々な利害関係者に対し責任を負うべきという考え方に基づきます。不祥事や環境問題への関心が高まる中、企業にとって必須の考え方となっており、ボランティア活動とは異なります。
CSV
Creating Shared Valueの略で、企業が社会問題を解決しながら経済的価値と社会的価値を同時に生み出すという考え方です。これは、経済効果と社会的価値の両立は難しいとされてきた従来の考え方を覆すものです。CSVは、事業の一環として社会課題に取り組む点でCSR(企業の社会的責任)とは異なり、利益を損なわずに持続可能な経営を実現することを目指します。
CTR
Click Through Rateの略で、広告のクリック率を意味します。これは、広告が表示された回数(インプレッション数)に対し、ユーザーが広告をクリックした回数の割合を示し、「クリック数 ÷ インプレッション数 × 100」で算出されます。CTRによって広告からの流入成果を把握できますが、これが直接コンバージョンに繋がるとは限りません。CTRを高めるには、ユーザーのニーズに合った広告クリエイティブや適切なキーワード、ターゲット設定が重要です。
CV率
アクセスしたユーザーがどの程度成果に繋がったかを示す指標です。Webマーケティングでは「成果」を意味し、「コンバージョン数 ÷ セッション数 × 100」で算出されます。商品購入の場合の平均は1~3%、BtoB業種の問い合わせや資料請求では約10%です。
DX
「ITの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変革させる」という概念です。ビジネスにおいては、デジタル技術やビジネスモデルを用いて組織を変革し、業績を改善することを指します。単なるIT化ではなく、これまでになかった製品やサービス開発、業務の見直し、働き方の変革などを通じて、市場競争力の強化や消費者ニーズへの対応を目指すものです。
LTV
Life Time Valueの略で「顧客生涯価値」を指し、一人の顧客が企業との取引を開始してから終了するまでの期間に、その顧客から得られると予測される利益の総額を表す指標です。「平均顧客単価 × 収益率 × 購買頻度 × 継続期間 – (新規顧客獲得コスト + 既存顧客維持コスト)」という計算式で算出されます。
SaaS
Software as a Serviceの略で「サース」と読みます。ソフトウェアをクラウドサービスとして提供する形態で、Gmailなどが代表的です。PaaS(Platform as a Service)は主に開発者向けで、アプリケーション実行に必要なミドルウェアをクラウドで提供します。IaaS(Infrastructure as a Service)は、サーバーやストレージ、ネットワークといったインフラをクラウドサービスとして提供するものです。
SPIN
新規顧客獲得が難しくなる中で、既存顧客の維持の重要性が高まり、LTVが重視されるようになりました。LTVは、「平均顧客単価 × 収益率 × 購買頻度 × 継続期間 – (新規顧客獲得コスト + 既存顧客維持コスト)」という計算式で算出されます。このLTVを高めるためには、アップセルやクロスセル、カスタマーサクセスといった施策が注目されています。
TAT
Turn Around Timeの略で、システム処理における要求から出力完了までの時間を指します。ビジネスにおいては「事業再生」と認識されており、経営状況の悪化した企業が業績回復のために中長期計画を立案することです。これには事業内容の見直しや財務、組織改編などが含まれ、その戦略を担う人をターンアラウンドマネージャーと呼びます。
アップセル
既存顧客により高性能な上位製品やサービス、あるいはオプションなどを提案し、購入単価を上げる営業手法です。新規顧客獲得のコストをかけずに売上を増やせるため、LTV(顧客生涯価値)向上に不可欠な戦略とされています。一方、ダウンセルは、価格の低い商材や下位の商材を提案して購入を促すこと、クロスセルは、検討中の商材に加えて別の関連商材を提案し、まとめて購入してもらうことで単価を上げる手法です。
ウェビナー
Webとセミナーを組み合わせた造語で、オンラインセミナーとも呼ばれます。インターネット環境があれば、場所を問わず配信・視聴が可能です。Zoomなどのツールを使えば難しい設定は不要で、パソコンやスマホなど様々な端末で利用できます。リアルタイム配信や録画配信、アーカイブ配信など、用途に応じて多様な形式で活用できます。
クラウドソーシング
Crowd(群衆)とSourcing(業務委託)を組み合わせた言葉で、企業がインターネットを介して不特定多数の個人や業者に業務を発注する新しい形態です。特定業者へのアウトソーシングとは異なり、人材採用コストを抑えつつ、必要な時にピンポイントで業務を委託できるのが利点です。業務の発注や受注には、ランサーズやクラウドワークスのような専門サービスへの登録が一般的です。
クロスセル
クロスセルとは、既存顧客に対し、購入を検討している商品と関連する別の商品を併せて提案することで、購入単価の向上を目指す営業戦略です。例えば、スマートフォンとケース・保護フィルムのセット販売や、風邪薬と栄養ドリンクの同時販売などが挙げられます。ECサイトのレコメンド機能もクロスセルを狙ったものです。
コアコンピタンス
企業の核となる強みであり、他社が容易に真似できない、社会に対して自信を持って提供できる優位性のある商品やサービスを指します。経営学者のゲイリー・ハメルとC・K・プラハラードによって提唱された概念です。評価の視点としては、移動可能性、模倣可能性、希少性、代替可能性、耐久性の5つが重要とされています。他社にはないこの独自の強みを活かして事業を展開する経営手法を「コアコンピタンス経営」と呼びます。
コモディティ化
市場投入時は高付加価値だった製品やサービスが、競合参入により機能や品質、ブランドで差別化できなくなり「一般化」することです。これにより価格競争に陥りやすくなります。この状況から抜け出すためには、ブランド戦略だけでなく、コミュニケーション戦略での差別化が重要です。
コンプライアンス
「法令遵守」を意味し、営業活動において法律や規則、社内ルールを守る基本的な姿勢を指します。就業規則や業務マニュアルの遵守はもちろん、モラルやマナーを意識することも重要です。コンプライアンス違反が発生すると、売り上げ減少だけでなく社会的信頼の喪失や、最悪の場合損害賠償請求に発展する可能性もあります。
ステークホルダー
企業活動によって影響を受ける利害関係者のことです。金銭的な関係を持つ株主や顧客だけでなく、官公庁、従業員、金融機関、競合会社、地域社会など、企業に関わるすべての人々を指します。ステークホルダーのうち、株主はストックホルダー、特に議決権を持つ大株主はシェアホルダーと呼ばれます。
セールステック
「Sales(営業)」と「Technology(テクノロジー)」を組み合わせた言葉で、テクノロジーを活用して営業・マーケティング活動の生産性を向上させる手法やツールのことです。代表的なツールとして、CRMやSFAがあります。インサイドセールスの増加に伴い、多くのBtoB・BtoC企業で活用が進んでおり、カスタマーサポートや人材開発の面からも営業活動を支援しています。
セールスプロモーション
「販売」と「販売促進」を組み合わせた言葉で、見込み顧客の購買行動に焦点を当て、商品やサービスの認知度向上から購入までを促す活動です。試供品の提供、期間限定キャンペーン、プロモーションビデオの放映などで購買意欲を刺激し、ニーズの顕在化を目指します。メディア広告、展示会、店頭活動、SNSキャンペーンなどが含まれます。
セミナー営業
新規顧客開拓や過去顧客の掘り起こし、顧客満足度向上などを目的とした営業活動です。ひとりのプレゼンターが複数企業にアプローチできるため、効率的な営業が可能です。近年ではウェビナーも活発に行われています。
ターゲット
マーケティングにおける商品やサービスの想定顧客層を指します。顧客層を限定し、性別・年齢・趣味嗜好などで細分化した市場に絞り込むことをターゲティング、その効率的な活動をターゲットマーケティングと呼びます。市場全体を対象とするのはマスマーケティングです。ターゲットが実在する集団を指すのに対し、ペルソナは実在しない架空の個人像を想定する点が異なります。
チャーンレート
Churn Rateと表記され、解約率を意味します。総顧客数に対する解約顧客の割合を示す指標で、「顧客離脱率」や「退会率」とも呼ばれます。チャーンレートには「カスタマーチャーンレート」と「レベニューチャーンレート」の2種類があります。
ニーズ
顧客の「〇〇したい」「〇〇になりたい」といった欲求を意味します。欲求を満たす手段が明確なウォンツとは異なり、ニーズは手段が明確ではありません。例えば、「雨の日でも快適に移動したい」はニーズ、「車が欲しい」はウォンツです。ニーズには、欲求が明確な顕在ニーズと、まだ自覚されていない潜在ニーズがあります。マーケティングや営業では、潜在ニーズを顕在化させることが重要です。
ニッチ
もともと西洋建築で「壁のくぼみ」を意味しますが、ビジネスにおいては「すき間市場」を指します。規模が小さく大企業が進出していないニッチ市場、誰も手をつけていないニッチ産業、ポピュラーではないが一定の需要があるニッチ商品といった使われ方をします。ニッチは「穴場」とも見なせるため、競争力に欠ける中小企業にとって大きな可能性を秘めています。戦略的にニッチな市場や分野を狙うことをニッチ戦略と呼びます。
ハイタッチ
LTV(顧客生涯価値)を指標に顧客を3つの層に分け、それぞれに最適なアプローチを行う手法です。LTVが最も高い顧客層をハイタッチ、中間層をロータッチ、低LTV層をテックタッチと分類します。限られた企業リソースは通常、ハイタッチ層に集中させます。
バッファ
本来は「緩衝材」や「余裕」「ゆとり」を意味します。IT分野では、処理しきれないデータを一時的に保存する「バッファメモリ」を指す言葉として使われ始めました。ビジネスにおいては、スケジュール、予算、人的リソースに対する余裕を意味することが多いです。「納期にバッファを持たせる」「商談の間にバッファを作る」といった使い方をします。
バリューエンジニアリング
商品やサービスの価値を「価格」と「機能や性能」の両面から見直し、高めていく手法です。単なるコスト削減ではなく、顧客ニーズを正確に捉え、価格を変えずに機能を向上させる、あるいは機能を変えずに価格を抑えることで、自社製品・サービスの利点から新たな価値を創造し、顧客に提供するという考え方です。
営業
会社の利益を目的として商品やサービスを販売し、契約を結ぶ業務、またはその業務を行う人を指します。どのような企業に、どのような方法で商品を売るかなど、マーケティング戦略の立案も担う場合があります。営業にはいくつかの種類があり、顧客や商材の特性によって手法が異なります。
営業代行
企業の営業活動を外部に委託することです。顧客獲得や契約締結に加え、テレアポ、テレマーケティング、顧客ニーズ分析、営業戦略立案、コンサルティングなど多岐にわたるサービスがあります。営業業務をアウトソーシングするメリットは、高いスキルを持つ人材を確保でき、教育コストをかけずに営業活動を迅速化できる点です。
機会損失
本来得られたはずの利益を失うことです。商品の破損などによる損失ではなく、営業や販売の機会を逃すことで発生する、未来的な損失を指し、「チャンスロス」とも呼ばれます。SFAなどのツールを活用し、案件や営業プロセスを適切に管理することが重要です。
限界利益
売上高から変動費を引いたもので、商品やサービスの売上による利益を示します。これを算出することで、自社の利益状況を客観的に把握できる指標となります。損益分岐点を分析すれば、利益を出すのに必要な売上高や、固定費・変動費の改善点が明確になります。営業利益とは固定費を差し引くかどうかが異なり、事業継続や経費見直しには限界利益と損益分岐点が重要視されます。
固定費用
売上に関わらず発生する費用で、人件費や家賃などが該当します。一方、変動費は生産量や販売量に比例して増減する費用で、原材料費や販売手数料などが含まれます。限界利益は売上高から変動費を引く、あるいは固定費と利益を足すことで算出され、利益の客観的な確認や事業継続の判断指標となります。損益分岐点計算の基礎となるため、これらを正確に理解することが重要です。
失注
商談が成約に至らず、商品やサービスの購入が見送られたりキャンセルになったりすることです。よくある原因には「競合他社に決まった」「情報収集のみが目的だった」「予算が合わなかった」「営業担当への信頼不足」などがあります。失注理由をヒアリングすることは、営業手法の改善に繋がります。
商圏
小売業や飲食業などで、来店を見込める顧客が住んでいる範囲、つまり集客が可能な範囲を指します。新店舗出店や既存店売上向上には、商圏を把握したマーケティングが不可欠です。実店舗を持たないBtoB企業でも商圏分析は必要で、商材によってはエリアマーケティングが有効なため、対象エリアの絞り込みが求められます。
商材
売るための物やサービスのことをいいます。商品も同じ意味ですが、主にビジネスとして売る目的がある物やサービスを「商材」ということが多いです。インターネット上ではビジネスやスポーツのノウハウなど、情報商材の取り引きも行われています。
商談
商品やサービスの取引に関する交渉や話し合いのことで、自社製品の提案から契約成立まで、合意形成を図りながら進めます。商談の状況は「確度」と「進度」で管理されます。商談の確度とは受注できる可能性、商談の進度とは顧客の検討段階を指します。特に初期段階や商談期間が長い場合は進度をこまめに確認し、適切にクロージングを行うことが重要です。
◆マネジメント
1on1
1on1ミーティングとは、会社組織において上司と部下が1対1で行う、人材育成を目的とした対話です。部下の成長を目的とし、部下を対話の主役とするのが大きな特徴です。仕事の成果ではなく、部下の悩みや望みなどを引き出すことに重点を置き、部下が主体的に話すことを促します。
BI
BI(ビジネスインテリジェンス)とは、膨大なデータを収集・蓄積・分析し、可視化する手法や技術、またはそのためのツールのことです。現代において、企業が定量的なデータに基づいて意思決定を行う上で重要な役割を担います。一般的なBIツールには、ETL、DWH、OLAP、データマイニング、予測分析などの機能が備わっています。
KPI
KPIは「重要業績評価指標」で、業務パフォーマンスを測る指標です。KGIは「重要目標達成指標」で、事業の大目標達成度を測ります。KGIが大目標、KPIがその達成に向けた日々の業務パフォーマンス指標となります。
OJT
OJTは「On the Job Training」の略で、実際の日常業務を通じて必要な知識や技術を身につける人材育成手法です。OJTは即戦力人材育成や研修コスト抑制にメリットがありますが、教える側の知識や技術に研修品質が左右されたり、体系的に学びづらいといったデメリットもあります。
OKR
OKRはObjective and Key Resultsの略で、目標と成果指標を関連づけて設定する目標管理手法です。米IntelやGoogleが採用し広まりました。目標達成を数値で評価できる指標をセットで設定し、少し高めの目標を設定することが理想とされています。KPIとは異なり、OKRは目標の明確化に優れています。
PDCA
PDCAはPlan→Do→Check→Actionの頭文字を取ったもので、これらのプロセスを繰り返し行うことで継続的な改善を目指すフレームワークです。提唱者の名前から「PDCAサイクル」とも呼ばれ、日本では品質管理に広く採用されています。近年は、Checkの代わりにStudyを入れたPDSAサイクルなど、時代に合わせて変化しています。
WFM
WFM(ワークフォース・マネジメント)とは、業務量やスキルに基づき、必要最低限の人員を適材適所に配置することで、サービスの品質や業務パフォーマンスを維持しつつコストを低減する手法です。WFMシステムは最適な人員配置やシフト管理を可視化し、テーマパーク、コールセンター、外食チェーン、病院などで広く導入されています。
エスカレーション
エスカレーションは「上申」を意味し、一次対応者がスキルや権限を超えた問題を上位の意思決定者に報告し、判断や業務を委ねる際に使われます。トラブル回避と効率的な業務遂行のため、エスカレーションすべきケースを明確なルールとして定めることが理想的です。
コミットメント
コミットメントとは、「責任」「約束」「献身」などを意味する名詞です。ビジネスシーンでは、確約・公約する、あるいは責任を持って関与・参加するといった意味で使われます。方針や責任の所在が明確であるほど、より強いコミットメントを得ることができます。
コンピテンシー
コンピテンシーとは、高いパフォーマンスを出す個人に共通して見られる特性を指します。優秀な人材の思考や行動パターンを分析することで、その高い成果を組織全体で再現する方法を明らかにします。個人の性格や動機、価値観といった目に見えづらい部分にも関わり、近年、成果主義志向の高まりとともに評価基準として採用する企業が増えています。
セールスイネーブルメント
セールスイネーブルメントとは、営業組織が長期的に成果を向上させるために、教育・研修、営業ツール開発、プロセス設計・管理などを総括的に行う強化・改善の取り組みです。個人やチーム間のばらつきを減らし、営業活動全体の根本的な力量を底上げすることを目指すもので、近年注目されています。
チームビルディング
チームビルディングは、組織が目標達成のために適切な能力を持つメンバーを構成したり、その思考や行動を目標に一致させるための取り組みです。日本では後者を指すことが多いでしょう。成功には目標の明確化と共有、役割分担の明確化、多様な意見を容認するコミュニケーションが重要です。曖昧な目標や役割はパフォーマンス低下や対立を招くため注意しましょう。
トークスクリプト
トークスクリプト(コールスクリプト)は、フィールドセールスやインサイドセールス、コールセンターなどで顧客に話す内容を事前に決めておくマニュアルです。これにより、個人の判断による企業方針からの逸脱を防ぎ、個々のトークスキルによる成果のばらつきを抑え、企業全体の品質と成績向上に繋げることができます。
ハイパフォーマー
企業や組織において、他の従業員よりも優れた成果を出す人材のことです。ハイパフォーマーは、知識や技能、貢献度といった目に見える特性に加え、コンピテンシーと呼ばれる成果に繋がる行動特性も持ちます。彼らの存在は、業績向上だけでなく、社員の意欲向上、後輩育成、人材開発、組織強化にも繋がり、特にインサイドセールスではセールスイネーブルメントに不可欠です。
フレームワーク
フレームワークは、問題解決や意思決定を効率的に行うための「ひな型」や「テンプレート」です。ビジネスでは、課題分析や方針決定などに活用され、MECEやPDCAといった有名なものがあります。
ベストプラクティス
ベストプラクティスは、最も効率的または最適とされる方法を意味し、業務効率化が最大のメリットです。ハイパフォーマーの手法を仕組み化し共有することで、組織全体の成果向上に繋がります。常にデータを分析し、更新していく必要があります。
マイルストーン
マイルストーンは、プロジェクトを完遂するための重要な中間目標地点です。スケジュール管理を容易にし、プロジェクトの遅延を防ぐ役割があります。細かく設定することで、モチベーションを維持し、スムーズな対応を促します。また、軌道修正やタスク漏れ防止にも役立ち、長期・複雑なプロジェクトでは必須です。
ロープレ
ロープレとはロールプレイングの略で、予行演習を意味します。仕事に慣れたりスキルアップを目的に、研修や接客、営業など様々な職種で実施されます。形式は大きく分けて3つです。特定の状況を設定するケース型ロープレ、現在や過去の問題を取り上げる問題解決型ロープレ、そしてグループで役割を交代しながら行うグループロープレがあります。
目標管理
目標管理(MBO)は、ピーター・ドラッカーが提唱した「目標による管理」というマネジメント手法です。上司が部下に自ら目標を設定させ、その達成度を管理することで、従業員の主体性とモチベーション向上、自ら考える能力の育成に繋がります。KPIが最終目標達成のための共有指標であるのに対し、MBOは個人目標であり上司とのみ共有され、人事評価に繋がる点が異なります。
◆ナレッジ
AI
AIとは「Artificial Intelligence」の略で、人間のような知性をコンピュータに実装する技術です。膨大なデータを学習し、複雑な作業を自動化できます。特に注目されるのは会話型の「生成AI」で、学習データをもとに画像、文章、動画などを生成して回答します。ChatGPTやGoogle Geminiなどが有名で、多様な分野で活用されており、さらなる進化が期待されています。
API
APIとは「Application Programming Interface」の略で、アプリケーションやプログラム同士を連携させる仕組みです。異なるシステム間で効率的なデータ共有や処理を可能にします。ウェブサイトやアプリが外部サービス(例:Google Maps)の機能を利用する際に使われ、ビジネスの効率化や新たな価値創造につながります。
ビジネスマナー
顧客や周囲との円滑なコミュニケーションと信頼関係構築の基盤となるものです。メール、電話、身だしなみ、名刺交換、敬語など様々な場面で求められます。特に営業職では、身だしなみや名刺交換が第一印象を左右します。時間厳守や約束を守ることも重要です。相手への思いやりと敬意を忘れず、状況に応じた適切な言葉遣いや態度を心がけることが大切です。
働き方改革
働く人々が多様な働き方を選択できる社会を実現するための改革です。単なる労働時間短縮ではなく、個々の能力発揮を促す柔軟で活力ある社会を目指します。長時間労働是正や非正規雇用の処遇改善などが進められており、労働者のワークライフバランス改善と生産性向上を図り、企業の文化変革も促すものです。
動画
パソコンやスマートフォンで見られるものを指し、映画館やテレビの「映像」と区別されます。YouTubeを中心に企業活用も進み、動画広告やインフルエンサーマーケティングが見られます。TikTokなどのショート動画も人気で、簡単に作成できる編集アプリも普及しています。VRや360度動画も広がり、娯楽だけでなく情報発信やマーケティングなど多岐にわたる役割を担う存在へと進化しています。
用語集は適宜追加・更新しています!
詳細な説明は「▶関連記事を見る」から確認いただけます。
お仕事を円滑に進めるには、用語を知るところから。
ぜひ、この用語集をお役立てください!
