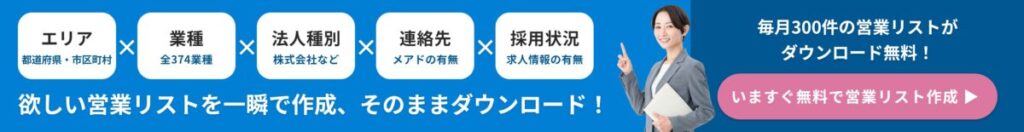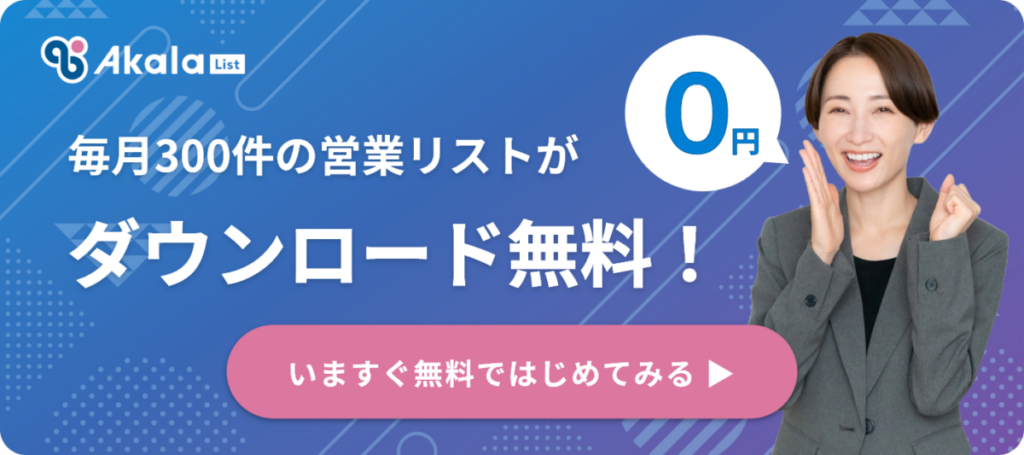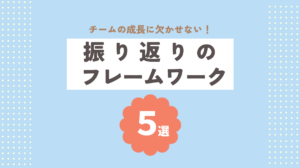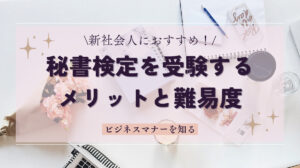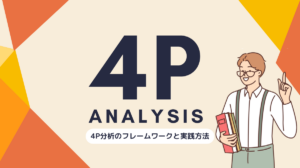最近は従来の対面営業からWeb会議システムを活用したオンライン営業に移行する組織が増えてきました。
これまでの営業手法は個々の能力によるところが大きかったのですが、オンラインに切り替わることで、営業手法やスキルを明文化する必要性が高まっています。
そんな動きのなかで注目されているのが「セールスイネーブルメント」です。
今回はセールスイネーブルメントについて、その意味や注目される背景、メリット・デメリット、実際の導入事例などを解説していきます。
セールスイネーブルメントとは?

セールスイネーブルメントとは、「成果を上げる営業人材を育てるために、組織全体で営業力強化・改善し仕組み化する」ことを意味します。つまり、成果を出す営業パーソンを輩出する人材育成のことを指します。
組織で成果を出している営業パーソンの営業手法やノウハウは、属人化しやすいことが特徴です。なぜなら、その人ならではのやり方や知識・経験に依存してしまうからです。
組織全体で成果を上げるためには、このような成果を出している営業パーソンの営業手法やノウハウを、組織の情報資産として蓄積し、他の営業パーソンのスキル向上に活用していかなくてはなりません。
営業手法やノウハウを営業資料などのセールスコンテンツの作成・送付やトレーニングに落とし込み、営業力の標準化をめざそうという点がポイントになります。
セールスイネーブルメント とは?
セールスイネーブルメント(Sales Enablement)とは、営業組織が長期的に成果を向上させる為に総括的に行う強化・改善の取り組みのことです。
営業組織の強化・改善の例としては、担当者の教育・研修から、営業ツールの開発、営業プロセスの設計・管理、担当者やチーム編成変更まで様々なものがあげられますが、これらは個別に短期的に行われることが少なくありません。
セールスイネーブルメントとは上記の活動を組織が総括的に長期に行うことを指しています。
個人や各チームごとに動きや成果にばらつきが出やすい営業組織において、一連の営業活動全体を見直し根本的な力量を底上げするセールスイネーブルというコンセプトは、近年企業からの注目を大きく集めています。
◆関連用語
BIツールを導入する企業が増えている
最近ではCRM(顧客管理システム)、SFA(営業支援ツール)、MA(マーケティングオートメーション)などの営業・マーケティングツールの市場が拡大し、現場に導入する企業が増えてきました。
このようなツールのことをBI(ビジネスインテリジェンス)ツールといいます。
営業・マーケティングツールを企業が導入することにより、顧客へのアプローチ状況や営業工数などの数値化・可視化が可能になります。そのため、営業スタッフの行動を分析し効率よく動けるよう改善できるのです。
さらに組織の営業成果を最大化させる仕組みを作る「セールスイネーブルメント」とのシナジーを発揮することが期待されています。
セールスイネーブルメントに注目が集まる理由

セールスイネーブルメントは、10年以上前の2013年頃に初めて注目されて以来、認知度はますます拡大しています。
調査機関CSO Insightsのレポート「Sales Enablement Grows Up」によると、セールスイネーブルメント専用の「人材」「プログラム」「機能」を持つ組織は、現在で3倍以上にまで拡大しています。
なぜ最近になってセールスイネーブルメントが再注目されるようになったのでしょうか?
オンライン営業へのシフト
2019年の新型コロナウイルスの感染拡大を背景に、営業手法は大きく変化しました。商談・資料送付・展示会などを非対面のオンラインで行うようにする企業が増えています。
また、紙で渡していたチラシやパンフレットはデジタル化、展示会はオフラインではなく、どこからでも参加できるデジタルプラットフォームが活用されるなど、従来の営業スタイルとは全く別のものとなりました。
Webマーケティングの導入
Webマーケティングの市場拡大や上記で述べたMA(マーケティングオートメーション)を導入する企業が増えてきたことも大きく影響しています。
Webマーケティングを導入することで多数の潜在顧客にアプローチすることができ、それに伴ってリードの獲得数やリードの質も向上しています。
MQLを活かすために営業力が必要
しかし、いくらリードの質や量が向上したからといって、必ずしも組織の売上まで自動的に向上するとは限りません。なぜなら、売上を上げるための重要なファクターは「営業」だからです。
たとえば、マーケティング部門やインサイドセールス部門から、リードナーチャリングによって質の高い(購買意欲の高まった)リードがパスされたとしても、営業が力不足であった場合は成約に結びつかないことも多くみられます。
MQL(マーケティング活動によって創出・育成された見込み度の高いリード)を成約に結びつけるために、セールスイネーブルメントは再度注目され、営業力の強化・改善の取り組みが必要とされているのです。
セールスイネーブルメントのメリット
セールスイネーブルメントのメリットは「営業スキルが数値化され、組織の情報資産になる」ことです。
成果を出せる営業パーソンが1人だけではなく、5人、10人と増えることで売れるために必要な手法やノウハウがMAやSFA、CRMといったツールに蓄積されていきます。
この蓄積されたデータを元に、さらなる営業スキルの向上が図れるというわけです。
セールスイネーブルメントのデメリット
セールスイネーブルメントのデメリットは、「コストがかかる」ことです。
なぜなら、ツールの導入費、検討までの人件費、社内浸透に時間がかかるなど、コストや時間がかかるからです。
最初は費用がかかってしまいますが、長い目で見れば将来、会社全体の営業力が強化されることによって売上アップが見込めるため、十分に費用対効果のある施策だと考えられます。
セールスイネーブルメントに必要なツール
セールスイネーブルメントでは、数値化された営業データを活用します。そのため、これらのツールを導入することで、様々なデータの分析が可能になり、セールスイネーブルメントの効果を高められます。
セールスイネーブルメントでは、大きく分けて以下の4つのツールが必要です。
・SFA(営業支援ツール)CRM(顧客管理システム)
顧客管理や営業プロセスを管理するためのツールです。
・インサイドセールスシステム
オンラインで商談ができるWeb商談システムのことです。
電話の機能とSFAやCRMを連携できるCTIは業務効率化、対応品質標準化のためにも必須でしょう。ほかにもCMS(コールマネジメントシステム)という、コール数や着信処理数、待ち呼、通話時間などをデータベース化して運営管理できるシステムも必要に応じて導入します。
・ウェビナーツール
オンラインでセミナーを開催できるツールです。リアルタイム配信、録画配信機能以外にも、点呼、アンケート配信、メール配信などの機能を備えたものもあります。
同時接続可能台数、料金などを比較検討して選んでみましょう。
・DCMS(セールスデジタルコンテンツ管理)
営業で使用する資料を管理するためのツールです。
取引先のニュースや財務状況が自動で取得でき、Gmailやカレンダーとの連携もできる「Senses」、送付した資料の閲覧時間が可視化され、さらに自動でアポ打診ができる「Sales Doc」などのツールが登場しています。
セールスイネーブルメントの流れ
セールスイネーブルメントの流れは、一般的に次の通りです。
| 1.担当者または、チームを立ち上げる 2.ツールを活用して営業情報を蓄積する 3.営業ノウハウを社内で共有する |
まずはセールスイネーブルメントの担当者、またはチームを立ち上げて社内での進め方を検討します。
次に、必要なツールを導入して、これまでの営業データを数値化して蓄積させます。
最後は、ツールに蓄積させた営業データをもとに、営業のノウハウなどを社内の営業パーソンに共有します。
特にインサイドセールスにおいては、データを活用して営業力を高める、データドリブンな営業の重要度が増しています。
データドリブン とは?
データドリブンとは、英語では「Data Driven」と表記され、定量的な情報を蓄積したビッグデータを分析し、企業の意思決定や課題解決に繋げる業務プロセスのことをいいます。
特にインサイドセールスでは様々なデータが取りやすいため、営業活動の効率化や成約率の向上に役立てることができます。
例えば、見込み顧客の選定から成約までの成功パターンを分析することで、より購買意欲の高い顧客フォーカスしてアプローチすることも可能になります。
ただし、分析結果を得るにはビッグデータの蓄積が必要になります。
どんなデータをどうやって集めるかを十分に検討し、間違いなく入力するところまでを設計して運用しなければなりません。
そのため、BI(ビジネスインテリジェンス)、MA(マーケティングオートメーション)、SFA(営業支援システム)、CRM(顧客管理システム)といったツールを積極的に導入する企業が増えています。
◆関連用語
セールスイネーブルメントの成功事例
セールスイネーブルメントを導入し成功した、営業代行などの営業コンサルティング事業を行う「株式会社セレブリックス」の事例をご紹介します。
株式会社セレブリックスは、セールスイネーブルメントの導入前は、営業パーソンのスキルや提案にばらつきがあることが課題でした。
しかし、セールスイネーブルメントを導入したことによって、誰でも一定以上の成果を上げられる「仕組み作り」に成功しました。
方法としては、「〇〇のような課題を持っている顧客には、この提案が有効的である」や、「相手に伝わりやすい資料を作成できれば、初回の提案からスムーズに商談を進められる」など、売上を立てるための営業手法を確立しました。
これにより、営業活動のデータ化や分析、新人や若手の教育、営業ツールの設計や社内運用を行った結果、誰でも最適な営業活動ができる環境が構築できました。
参考:【セレブリックス×UPWARD 前編】再現性のある営業組織へと導き、営業一人ひとりの創造性を引き出す
まとめセールスイネーブルメント
セールスイネーブルメントを導入している企業は多く、成功事例も増えてきています。
自社でセールスイネーブルメントを導入するには、メリット・デメリットをしっかりと理解した上で、導入を検討しなければなりません。
組織全体の営業力を強化するためには、セールスイネーブルメントはとても有効的な手段であると言えます。セールスイネーブルメントに特化したツールも続々登場しています。自社の営業活動を仕組み化することは、これからの営業に必要な手法となってくるので、セールスイネーブルメントの考え方で営業組織を強化していきましょう。
Akalaリストとは、「製造業の中小企業リスト」「IT企業一覧」などの絞り込み条件を選ぶだけで、ニーズにマッチした企業を抽出できる「営業リスト作成ツール」です。
最短30秒で営業リストが作成でき、さくっとダウンロード可能。CSVもしくはエクセルファイルでダウンロードできるのでExcelはもちろんGoogleスプレッドシートでそのまま開けます。
企業情報の鮮度と精度にもこだわっています。各企業のIR情報や官公庁の統計資料などの一般公開されている情報に加えて、日本国内の500万を超える法人データを収集し、高い精度で電話番号やメールアドレスなど連絡先のクレンジング・名寄せ処理を行っています。
さらに生成AIを活用して、企業の重要情報を要約。ぱっと見でどんな企業かわかる「商談メモ」も作成済みです。
いまなら毎月300件無料ダウンロードできる!
いまなら会員登録するだけで毎月300件の営業リストが無料ダウンロードできます!
有料プランへの切り替え手続きをしない限り、料金を請求することはございません。無料プランは電話番号もクレジットカードの登録も不要なのでご安心ください。
弊社保有の情報は、全国の法人データです。なかでも、企業リストを主体としております。
株式会社、合同会社などの企業情報となるため、法人番号を持たない公立学校や店舗などのリストはご用意できません。
Akalaリストは最新のAI技術を活用し、人の手で行う作業を減らすことでコストを抑えているため、無料でご利用いただけます。新規開拓営業など、ぜひお役立てください。
AIが収集する各企業のIR情報や官公庁の統計資料など、一般公開されている大量の企業情報を独自の技術によってデータベース化しています。
▼Akalaリストについてよくある質問はこちらから!
https://note.akala.ai/help/