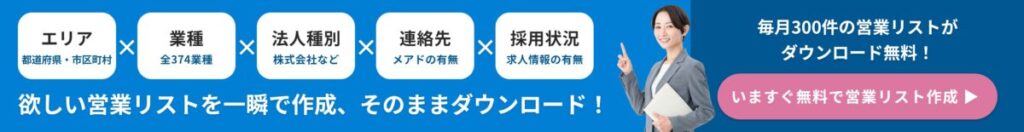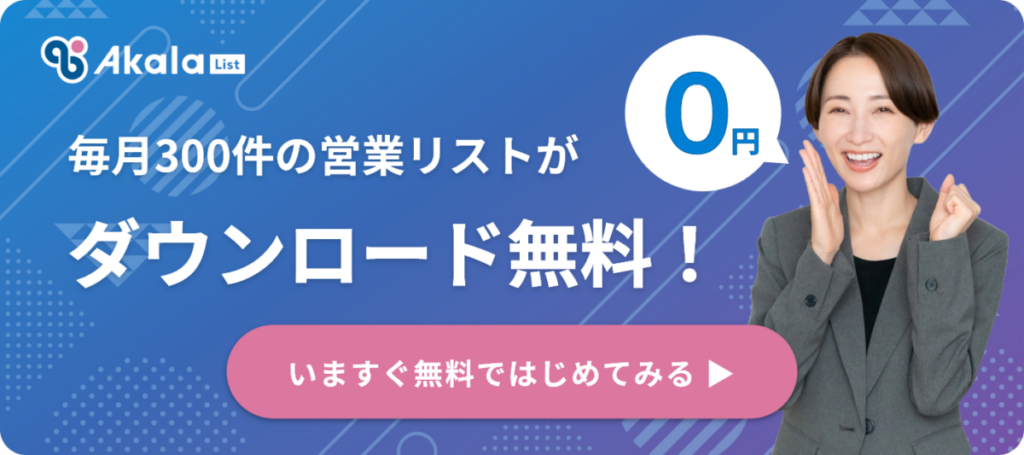営業職にとって避けて通れない「コールドコール」。
リストを見ながら見ず知らずの相手に電話をかけるのは、正直なところツライ……という方も多いのではないでしょうか? しかし、ちょっとした工夫とコツを押さえるだけで、驚くほど成功率を高めることができます。
今回は、テレアポのノウハウを蓄積する弊社が実践する「コールドコールの極意5選」をご紹介します。これを読むことで、ただの「電話営業」が「成果につながる商談の第一歩」へと変わるはずです!
コールドコールとは?
コールドコールとは、事前の接点や関係性のない相手に対して、電話をかけて商談のきっかけをつくる飛び込み型の営業手法のことです。 テレアポ や BDR とも呼ばれ、特にBtoBの営業現場では今もなお主流のアプローチ方法となっています。
実際に訪問する「飛び込み営業」と比べると時間効率がよく、広範囲にアプローチできるのが特徴です。しかしその分、「電話口で断られる」「話を聞いてもらえない」といったハードルも多く存在します。
コールドコール とは?
コールドコールとは、いわゆる飛び込み型の電話営業の手法で、まったく面識のない相手に架電することをいいます。
その際に使用するリストも「コールドリスト」と呼ばれます。
コールドとはcoldのことで「冷たい」という意味です。
BtoB営業では新規顧客開拓のため、相手の代表電話にいきなり架電をすることになります。
相手のニーズや興味の度合いはおろか、担当者の氏名や担当部署名も把握しないまま架電するため、警戒心から受付ブロックされてしまう可能性が高いです。
コストを抑えて見込み顧客リストが獲得できるのはメリットですが、アポイントの獲得などの成果を出すにはそれなりのスタッフ数とコール数が必要になることがデメリットになります。
コールドコールの成果率をあげるには、ある程度ターゲティングを行い、少しでも自社商品やサービスに興味を持つ可能性の高い企業に絞ってリストを作成する必要があります。
◆関連用語
cold=熱意がないという意味
コールドコールの「コールド」はcoldのことですが、決して「冷たくあしらわれる」という意味ではありません。自社の商品やサービスに対して熱意を持っていないという意味でのコールドです。
コールドコールというと「数打ちゃ当たる戦法」だと思われがちですが、コツを抑えればテレアポの精度はぐっと上がります。
コールドリストとコールドリード
コールドコールとよく似た言葉に、コールドリストとコールドリードがあります。
コールドリストとは、これまで自社とまったく接点のなかった企業リストのことをいいます。ここからテレアポ(コールドコール)などの手法で、見込み顧客を獲得していくためのリストになります。
逆に過去に接点のあった見込み顧客や顧客をリスト化したものをハウスリストといい、営業リストはコールドリストとこのハウスリストに分けられます。テレアポなどの施策の結果、コールドリストからハウスリストへ転換することも可能です。
また、コールドリードとは潜在顧客のことで、将来的に商品やサービスを購入する可能性があるものの、現時点では興味が薄く、検討段階にも至っていない見込み顧客のことをいいます。
コールドコールのメリット
コールドコールは「数打ちゃ当たる」「当たって砕けろ」の精神で電話をかけ続けることだと思われがちですが、BtoBマーケティング、BtoB営業では非常に重要な役割があります。
コールドコールのメリットに注目してみましょう。
コストがかからない
コールドコールのいちばんのメリットはコストがかからないことにあります。
従来の飛び込み営業に比べると、時間や人的リソースはそれほど必要ありません。電話さえあればアプローチが始められるので、広告やホームページにお金をかけられない場合も効果を発揮します。
アプローチ数が増える
移動の必要がないため、担当者ひとり当たりのアプローチ数は格段に多くなります。効率良く営業活動を行えることはもちろん、新たな潜在顧客層へのアプローチも可能になります。
関係構築のきっかけになる
コールドコールがきっかけとなって、架電先の企業に自社商品やサービスを認知してもらうことができます。ニーズが発生したときに検討対象になることもあるため、コールドコールは無駄とはいえません。
自社商品への理解が深まる
コールドコールを行うには、自社商品やサービスを深く理解する必要があります。そのうえで、電話でどのように切り出すか、どのようにニーズを聞き出すかなど、営業トーク力も磨かれます。
コールドコールのデメリット
一方で、コールドコールにはデメリットもあります。
成約率が低い
コールドコールはニーズがあるのかどうかもわからない企業に架電をするため、アポの獲得はとても難しいといえます。そのため、どうしてもコール数を増やさなければなりません。
悪い印象を与えてしまう
BDRは新規顧客開拓のため、電話をかけてアポを獲得するのが目的です。とはいえ、お付き合いのない企業への架電になるため、好意的に受け入れられるとは限りません。営業電話を嫌う企業は多いため、悪い印象を与えてしまうことがあります。
BDRの役割について、以下の記事もあわせて読んでみましょう。
精神的負担が大きい
コールドコールは「ガチャ切り」されることもあります。ときには厳しいご意見を受けることもあるでしょう。そのため、コールドコール担当者には大きな精神的負担がかかってしまいます。
コールドコールの極意5選
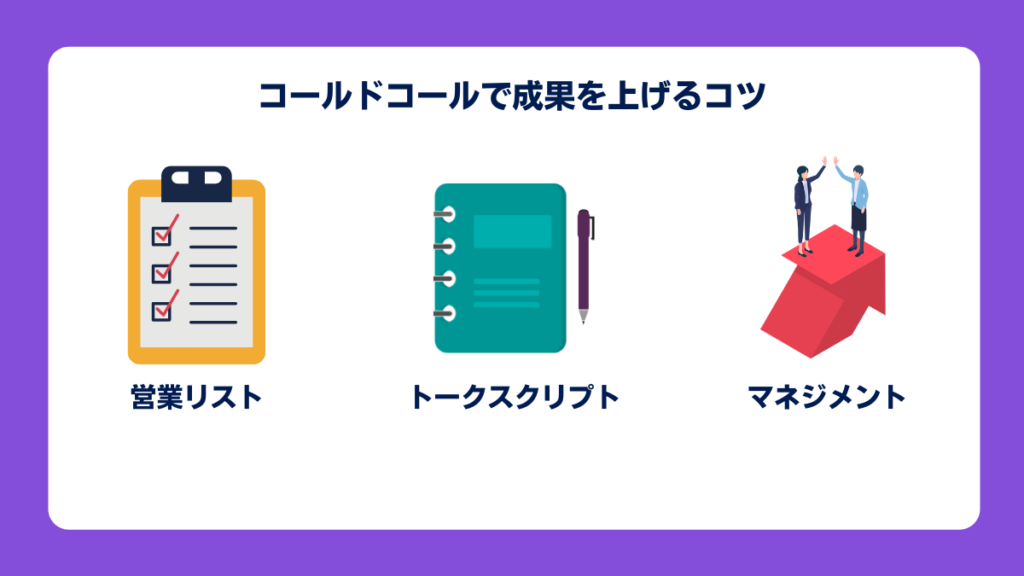
コールドコールによるテレアポで成果を上げるコツを「極意」としてまとめました。
【極意①】“断られない第一声”を用意する
最初の数秒で勝負は決まります。「お世話になっております、○○株式会社の△△と申します…」だけでは、相手の印象に残らず、営業だと思われてすぐに切られてしまう可能性が大きいでしょう。
ここで大切なのが、相手に“自分に関係ある話かも”と思わせる切り口です。
「突然のお電話失礼いたします。○○業界の企業様向けに、●●のご支援をしている△△と申します。」
といったように、“あなたに関係がありますよ”というメッセージを冒頭に込めるだけで、相手の耳が開きやすくなります。
【極意②】「売り込み」ではなく「リスニング」を意識する
コールドコールの目的はその場で売ることではなく、“アポを取ること”。つい商品の魅力やサービス内容を長々と説明したくなりますが、相手にとっては迷惑電話になってしまう可能性が高いです。
ここで大切なのは、会話の主導権を“相手側”に渡すこと。
「現在、○○に関して何か課題を感じていらっしゃることはありますか?」
といったように、相手の課題やニーズを引き出す質問をすることで、自然な会話の流れを作れます。相手が話してくれた内容をもとに、「実はそれ、弊社でもサポートできるかもしれません」と、次につなげましょう。
【極意③】断られても“二段構え”で返す
「結構です」「今は興味ありません」こんなフレーズを一度でも聞いたことがある方は多いでしょう。でも、ここですぐに電話を切ってしまうのはもったいないです!
「断り文句」には、いくつかパターンがあります。
- 「今忙しい」→ 別の時間に再提案
- 「興味ない」→ ニーズがないのではなく、理解されていないだけ
この場合の返し方はこんな感じです:
「かしこまりました。ご多忙の中、恐縮です。ただ、○○の件で他社様からもご相談が多い内容ですので、1〜2分だけポイントだけお伝えしてもよろしいでしょうか?」
このように、一歩踏み込むことで「話してもいいかも」と思ってもらえる可能性が生まれます。
【極意④】トークスクリプトは“設計”して、“棒読み”は避ける
トークスクリプト は、営業活動においての設計図。しかし、「スクリプト通りに話そう」と意識しすぎると、機械的で冷たい印象を与えてしまいます。
ポイントは、「話す内容は設計図、話し方はアドリブ」という意識を持つこと。特にコールドコールの場合は、「相手に電話を切られない話し方」「興味を持ってもらいやすい話の流れ」が重要です。
- 導入トーク
- ヒアリングの質問
- 断られたときの返答
- クロージングの一言
といった場面ごとのフレーズを事前に用意し、会話の中では自然に組み合わせるように意識しましょう。何パターンか用意してテストを行い、成果の出やすいトークスクリプトへブラッシュアップしていくこともできます。
【極意⑤】架電数と振り返りで、勝率が見えてくる
どんなに優れたトークスキルがあっても、数をこなさなければ成果は見えてきません。しかし、「ただ闇雲に架ける」のではなく、毎日の電話営業の結果を必ず記録し、振り返ることが重要です。
以下のような項目を記録してみましょう
- 架電数
- 接続数
- 会話できた件数
- アポ獲得数
- よく出てくる断り文句
- 自分の返し方と結果
これを分析することで、自分の弱点や改善点がはっきりします。また、断られたトークをどう改善したかを記録しておけば、チームでのノウハウ共有にも役立ちます。
営業リストにも工夫が必要!
コールドコールといっても、ただやみくもに電話をかけるのはNGです。必ず事前にリサーチをして、業種や企業規模などを絞り込むターゲティングが必要になります。
上場企業か非上場企業か、従業員数はどれくらいか、スタートアップか大企業かなど、自社の商品やサービスに興味を持ってもらえそうな企業を絞り込んでリストアップします。
営業リストの作り方については以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ

近年では営業・マーケティングの主戦場はインターネットになりつつありますが、ターゲット層である企業の情報収集チャネルもデジタル化したかといえばそうでもありません。
コールドコールは古い営業手法だと思われがちですが、コツを抑えていけば成果を上げることも可能です。
顧客数が限られているBtoB企業だからこそ、コールドコールで潜在顧客に広くアプローチする戦略が効果的だと考えることもできます。そのためにも「営業リスト」「トークスクリプト」「マネジメント」は常にPDCAを回しながらブラッシュアップしていくようにしましょう。
コールドコールはどうしても精神的負担が大きくなってしまうため、1on1やロープレを実施することでフォローアップすることも大切です。
Akalaリストとは、「製造業の中小企業リスト」「IT企業一覧」などの絞り込み条件を選ぶだけで、ニーズにマッチした企業を抽出できる「営業リスト作成ツール」です。
最短30秒で営業リストが作成でき、さくっとダウンロード可能。CSVもしくはエクセルファイルでダウンロードできるのでExcelはもちろんGoogleスプレッドシートでそのまま開けます。
企業情報の鮮度と精度にもこだわっています。各企業のIR情報や官公庁の統計資料などの一般公開されている情報に加えて、日本国内の500万を超える法人データを収集し、高い精度で電話番号やメールアドレスなど連絡先のクレンジング・名寄せ処理を行っています。
さらに生成AIを活用して、企業の重要情報を要約。ぱっと見でどんな企業かわかる「商談メモ」も作成済みです。
いまなら毎月300件無料ダウンロードできる!
いまなら会員登録するだけで毎月300件の営業リストが無料ダウンロードできます!
有料プランへの切り替え手続きをしない限り、料金を請求することはございません。無料プランは電話番号もクレジットカードの登録も不要なのでご安心ください。
弊社保有の情報は、全国の法人データです。なかでも、企業リストを主体としております。
株式会社、合同会社などの企業情報となるため、法人番号を持たない公立学校や店舗などのリストはご用意できません。
Akalaリストは最新のAI技術を活用し、人の手で行う作業を減らすことでコストを抑えているため、無料でご利用いただけます。新規開拓営業など、ぜひお役立てください。
AIが収集する各企業のIR情報や官公庁の統計資料など、一般公開されている大量の企業情報を独自の技術によってデータベース化しています。
▼Akalaリストについてよくある質問はこちらから!
https://note.akala.ai/faq-category/akala-list