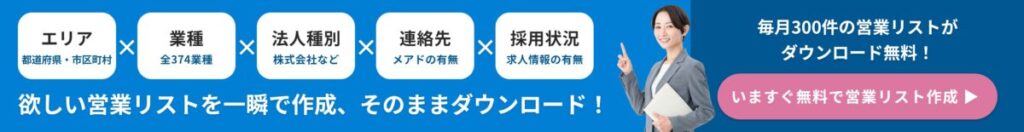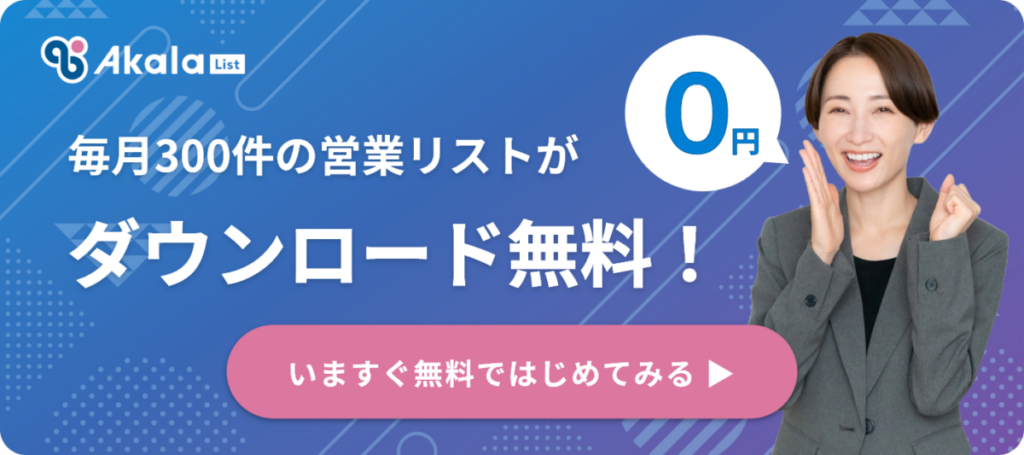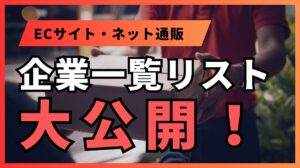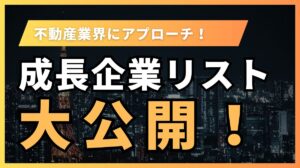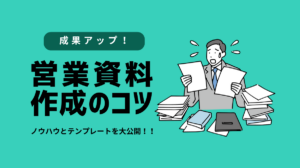中小企業と大企業の違いはどこにあるのでしょうか? マーケティング施策を考えるとき、営業リストを作るときに考慮すべきことは何なのでしょうか?
この記事では、中小企業と大企業の定義について紹介します。さらに中小企業と大企業の違いを「給与」「組織」「仕事の進め方」について比較。
中小企業と大企業の違いを踏まえた上で、営業手法の特徴をそれぞれわかりやすく解説します。
中小企業の定義

中小企業の定義については、中小企業基本法に明記されています。
中小企業基本法では、業種ごとに中小企業者の定義を設けており、資本金の額または出資金の総額および従業員の数のいずれかを満たしているかどうかで判断できます。
| 業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
| 製造業その他 | ・資本金または出資の総額が3億円以下 ・従業員数300人以下 |
| 卸売業 | ・資本金または出資の総額が1億円以下 ・従業員数100人以下 |
| サービス業 | ・資本金または出資の総額が5000万円以下 ・従業員数100人以下 |
| 小売業 | ・資本金または出資の総額が5000万円以下 ・従業員数50人以下 |
なお、この中小企業の分類は中小企業基本法による定義であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われる範囲は異なります。
例えば、租税特別措置法では、「資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人」または「常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人」が大規模法人とされています。ざっくりと中小企業と大企業を分けるときは、この定義がわかりやすいですね。
中小企業と大企業の違い
大企業については、法律で定めた定義はありません。中小企業基本法で定められた中小企業の範囲より規模が大きい企業を大企業とみなすのが一般的です。
それでは中小企業と大企業には、どのような違いがあるのでしょうか。その特徴について具体的にみていきましょう。
給与面で比較
給与について、大企業と中小企業では次のような違いがあります。
・大企業
給与の体系がしっかりしており、査定基準が明確。中小企業と比較して給与水準が高い傾向にあります。
・中小企業
一般的には大企業に比較すると、給与水準が低い傾向に。また、大企業のように査定の基準がはっきりと決まっていないケースもあります。
組織の成り立ちで比較
組織について、大企業と中小企業では次のような違いがあります。
・大企業
従業員数が多く、年功序列の風潮が残っている企業もあります。社内のルールや業務フローが決められているため、担当者・現場での裁量は多くありません。決裁を得たいことがある時など承認の手続きが複雑になりがちで、長時間を必要とする場合があります。
・中小企業
従業員と経営層の距離が近く、柔軟に業務に対応できる特徴があります。大企業に比べるとコミュニケーションも活発で、現場や個人の提案も通りやすい環境です。一方、仕事の進め方は人数が少ない分、一人で担当する仕事の領域が大きくなります。
仕事の進め方で比較
仕事の進め方について、大企業と中小企業では次のような違いがあります。
・大企業
大企業は名前が知られており、社会的信頼が高いため、入社年次が短い担当者でも顧客や取引先とスムースに商談できます。また、中小企業に比べると金額の高い仕事を担当している場合もあります。仕事の分担については、組織で縦割りの分業制です。
・中小企業
一人でさまざまな分野の仕事を担当している場合もあります。入社年次や年齢に関係なく、役職についていることもあります。
中小企業の割合は日本企業の99%以上

日本企業における中小企業の割合は99.7%です。全企業の従業員のうち69%の人が中小企業に勤務しています。付加価値額(製造業)は、大企業が約50兆円で47%、中小企業が約57兆円で53%を占めています。
中小企業と大企業で異なる営業手法
大企業に対する営業をエンタープライズ営業といいます。ここでは大企業と中小企業に対する営業手法の違いをそれぞれみていきましょう。
大企業への営業手法の特徴(エンタープライズ営業)
大企業へ新規アポをとる際の一般的な手法と特徴をご紹介します。
・リード数が少ない
大企業の割合は法人企業の0.3%と少なく、そのためリード数も少なくなります。大企業には競合他社の存在もあり、なかなか新規にアプローチができません。大企業は資料請求などのアクションをしなくても情報が入手できるので、アプローチには工夫が必要です。
・契約に至るまで時間がかかる
大企業には複数の部署があるため、契約に至るまで時間がかかります。それは製品・サービスを導入する部署と購入契約をする部署が異なるからです。予算管理を別の部署で行うこともあります。さらに関連する部署があると、社内調整が必要な場合もあり、契約まで時間を必要とします。
・売り上げが大きい・継続につながる
エンタープライズ営業は難しい反面、契約できれば売り上げは大きくなる傾向があります。従業員が共通して使う製品・サービスであれば、従業員の数が多い分、売り上げに反映します。
大企業では部署ごとに違う製品・サービスを使うと効率が悪くなるので、同じものに統一するケースがほとんどです。また、製品・サービスの更新時には使い勝手が変わることを嫌って、同じシリーズのもので契約を更新してもらえる可能性も高くなります。
・意思決定者にたどり着きにくい
大企業に製品・サービスを導入しようとする場合、最終的に誰が決裁をするか外部からはわかりにくいものです。多くの場合、金額や内容によって最終決定者が決まっています。取締役会で決める必要があるもの、部長・課長・係長の決裁で決められるものなど、さまざまです。
実務は担当者や課長クラスが対応しても、最終的な決定はより上位の職位の人であること。決定者の考えが契約に影響を与えることもあります。
法人営業のためのフレームワーク「BANT」についてもぜひ知っておきましょう。
中小企業への営業手法の特徴
中小企業へのアプローチ方法と営業手法の特徴についてご紹介します。
・企業数が圧倒的に多い
中小企業の割合は、大企業の0.3%と比べて圧倒的に多く、市場規模にもボリュームがあります。企業数が多いので、初期の営業で訪問することは効率が悪くなりがちです。
そのため、初期はインサイドセールスで営業します。大企業に比べると1契約あたりの売り上げは少ないので、効率をあげて数多く契約することがポイントになります。
インサイドセールスの具体的な手法や効果については以下の記事に詳しくまとめています。
・迅速な対応が必要
大企業の場合は、さまざまなプロセスを経て成約に至ります。中小企業の場合は、問い合わせなどリードの段階から契約までのスピードが速いので、迅速にアプローチする必要があります。
・柔軟な対応が必要
大企業では組織が縦割りの分業制です。社内ルールで決定権限者の職位が明確に決まっている場合がほとんどです。
大企業に対して、中小企業はそれぞれ体制が多様で、大企業のようなルールがなく、決まりが曖昧な企業もあります。すべての決定を社長がしている場合もあれば、すべて現場に任せている企業もあるのです。この辺りは大企業とは違い、柔軟に対応していく必要があります。
・費用対効果は大企業より厳しい
中小企業が製品・サービスを導入する場合の費用対効果の判断は、大企業よりシビアな傾向があります。導入するコストに見合うメリットが明確にならなければ契約しません。
また、はっきりとした効果の見通しがなければ、長期契約は難しいでしょう。大企業であれば、製品・サービスの更新の際に使い勝手を優先し、既存のシリーズを選ぶこともあります。しかし、中小企業の場合、よりコストが低い製品・サービスに乗り換えることも十分考えられます。
そのため、変更に対応できるような柔軟な契約やトライアル料金を設定するなどして、ハードルを下げることが有効です。中小企業の場合、人事異動などで担当者が変わることも大企業ほどありません。そのため、関係性を築いて、信頼を高めていくことが長期的な成功につながるでしょう。
また、1契約あたりの売り上げが小さいので、効率的に数多くの企業にアプローチする必要があります。
まとめ
中小企業は、中小企業基本法により定義されています。そして、大企業の割合はわずか0.3%で、残りの99.7%は中小企業です。
大企業は組織やルールがしっかりしている一方、手続きに時間のかかる傾向があります。中小企業の組織はさまざまです。大企業に比べればルールなどが曖昧なところもあります。一方、意思決定のプロセスが少ないので、迅速な判断ができます。
大企業に対する営業手法は、エンタープライズ営業です。競合他社が多く、営業としては難しい部分もあります。しかし、契約ができれば、1契約あたりの売り上げが高いので、成果を上げやすいでしょう。
これに対して、中小企業に対する営業の初期はインサイドセールスが有効になります。大企業に比べ圧倒的に企業数が多いからです。1契約あたりの売り上げが少ないので、効率的に営業する必要があります。
新たに中小企業の営業を担当される場合は、大企業との違いに驚かれるかも知れません。しかし、中小企業に対する営業に最適化し、長期的に信用を勝ち取れば成約につながります。
Akalaリストとは、「製造業の中小企業リスト」「IT企業一覧」などの絞り込み条件を選ぶだけで、ニーズにマッチした企業を抽出できる「営業リスト作成ツール」です。
最短30秒で営業リストが作成でき、さくっとダウンロード可能。CSVもしくはエクセルファイルでダウンロードできるのでExcelはもちろんGoogleスプレッドシートでそのまま開けます。
企業情報の鮮度と精度にもこだわっています。各企業のIR情報や官公庁の統計資料などの一般公開されている情報に加えて、日本国内の500万を超える法人データを収集し、高い精度で電話番号やメールアドレスなど連絡先のクレンジング・名寄せ処理を行っています。
さらに生成AIを活用して、企業の重要情報を要約。ぱっと見でどんな企業かわかる「商談メモ」も作成済みです。
いまなら毎月300件無料ダウンロードできる!
いまなら会員登録するだけで毎月300件の営業リストが無料ダウンロードできます!
有料プランへの切り替え手続きをしない限り、料金を請求することはございません。無料プランは電話番号もクレジットカードの登録も不要なのでご安心ください。
弊社保有の情報は、全国の法人データです。なかでも、企業リストを主体としております。
株式会社、合同会社などの企業情報となるため、法人番号を持たない公立学校や店舗などのリストはご用意できません。
Akalaリストは最新のAI技術を活用し、人の手で行う作業を減らすことでコストを抑えているため、無料でご利用いただけます。新規開拓営業など、ぜひお役立てください。
AIが収集する各企業のIR情報や官公庁の統計資料など、一般公開されている大量の企業情報を独自の技術によってデータベース化しています。
▼Akalaリストについてよくある質問はこちらから!
https://note.akala.ai/faq-category/akala-list